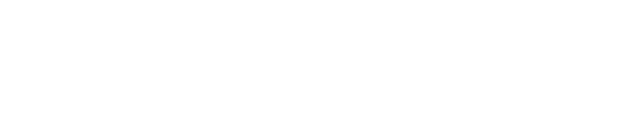<半兵衛のひとりごと 03>
「黄金比の限界と可能性」
「黄金比の限界と可能性」
「神は死んだ。」とニーチェが唱えて以降、アートの世界でも価値基準が大きく変わり、20世紀初頭には革新的な作品が数多く生み出されました。
建築界では、諸事情により他の芸術分野よりやや遅れて変革の波がやってきました。そのせいもあり、モダニズムの頃まで黄金比に縛られている建築家もいました。
「黄金比」は、絶対的な美の基準として、これまで多くの芸術家・建築家に親しまれてきました。
その時代背景には、様々な政治的事情がありました。
特に建築は、時の権力者の威厳を示すために政治利用されるのが常でした。
失敗すれば粛清(国によっては死刑)です。建築家は個人的な美意識が原因で失敗しないよう、誰もが認める基準を模索しました。そこで、自然界の法則に行き着いたのです。
これぞ神がつくり給うた絶対的な基準であり、作品を否定することは神を否定することになるのです。こうして作家は自分の身を守ることができたのです。
元々、誰もが美しいと思う比率を想定してそれに見合う法則を探し出したわけですから、誰も疑うことはありませんでした。すべて丸く収まったというわけです。
「黄金比」のルーツとして、巻貝の成り立ちをフィボナッチ数列に置き換えるところが、いかにも西洋的で興味深いところです。
自然をも人間のつくったルールに嵌め込むのですから、神をも恐れぬとんだ神信仰者です。
ここでニーチェの話に繋がってきます。
以前は、人間というのは神が自分の姿に似せてつくった創造物であると信じられていました。これは疑う余地のない神信仰の根本的な考え方でした。
ところが、時代の変化とともに、その考えも揺らぐこととなりました。神は、逆に人間がつくり出した創造物だというのです。だから神は人間の姿をしているというわけです。それまでは、権力者にとって神の存在は、民衆の感情をコントロールするのにとても都合がよかったのです。
当時は宗教さえも政治利用されていたわけですが、時代が変わり、すべてが曝け出されることになり、その象徴として「神は死んだ。」となったわけです。
本当の神の存在はともかく、時代は実存主義から構造主義へと変わり、様々な分野で革新が進みました。パラダイムシフトです。特に芸術の世界では実質的な制約が少なく、その「表現」方法は飛躍的に向上しました。厳密に言うと、「表現」という考え方まで否定されています。
「表現」=実存主義的「再現」であり、本来の目的であるはずのものが手段でしかなくなってしまう自己矛盾に陥ってしまうからです。
それに気付かない二流アーティストは作品で「自分を表現」しようし、一流アーティストは「普遍性」を追求します。
このような時代背景があり、建築家も黄金比に縛られる理由がなくなりました。
そもそも黄金比を確認できるのは図面上だけで、実際には人の目線からは確認不可能です。それこそ神の目線でのみ可能でしょう。
現在では、「見る主体」が知覚する断片の集積が、いかに構造化されていくかというプロセスまで考える時代に来ています。その先駆けが20世紀初頭のアヴァンギャルドたちであり、彼らの実験的な作品にはアイデアが溢れています。
残念ながら、多くの前衛芸術家たちの難解な理論は一般大衆には理解されず、ファッションとして消費されていくことになります。
現在でも大衆はピカソよりラッセンが好きだし、デュシャンよりバンクシーの方が高く売れるのです。
とは言え、私は黄金比が時代遅れで無意味なものとは言いません。多くの人が美しいと思う比率であることは変わりありませんし、まだまだ採用する建築家も多くいます(その意味を理解しているかどうかは分かりませんが)。
大事なのは、それを踏まえたうえで次に何をするかです。
「調和・安定・均衡」を測る「ものさし」が意味を無くしたとき、排除されてきた「不調和・不安定・不均衡」とのはざまには多くの可能性が秘められているのです。
「心地よさ」の知覚の話の中で、多種多様な「ものさし」の曖昧性と脆弱性がカギになると言いましたが、これは実は言語そのものの属性でもあります。
差異の体系である言語が、人々のコミュニケーションを通して、忘却と覚醒の危機にさらされながらも、緩やかに変化し、その体系性を維持しています。
同様に「心地よい」という感覚は、安定と逸脱との対比の中ではじめて自覚できるという面も備えています。
これはほんの一例で、多くの心的現象が、人間の思考を支配している言語のメカニズムに深く関係しており、逃れられないということ、そして私たちがそれを理解することで、様々な仮説を立てられる可能性が見えてくるのです。